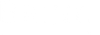この夏、BRINGのWUNDERWEARはフォトグラファーと、カナダ北極圏に位置するサマセット島へ共に旅をしました。
INTERVIEW 17 | サマセット島、夏の北極圏。アドベンチャーフォトグラファー 福本玲央 ベルーガの声を追う旅
2025.12.18
序章 | 旅という⾔葉の輪郭
たび【旅】──
住む⼟地を離れて、⼀時、他の離れた⼟地にいること。 また、住居から離れた⼟地に移動すること。
⾃宅以外の場所に、臨時にいること。
Googleで「旅」と検索すると、こんな定義が出てくる。 どうやら“⾃宅から離れること”を旅と呼ぶらしい。 それって、なんなら「おでかけ」の⽅がしっくりくるんじゃないか? そう思いつつ
も、天下のGoogle様がそうおっしゃるのだから、⼀旦は飲み込むしかない。
私が想像する「旅」という⾏為は、もう少し曖昧で、アンニュイなものだ。 スナフキンがパイプをくわえて⾵のままに漂うような、静けさと⾃由が同居するような感覚。 “移動”というより、“漂流”に近いのかもしれない。
居たたまれなくなって、「旅」と「旅⾏」の違いを調べてみた。するとこんなふうに出てきた。
「旅」と「旅⾏」の主な違いは、
過程を重視するか(旅)、⽬的地や観光を重視するか(旅⾏)、 そしてそれに伴う「学び」や「⾮⽇常」の要素が強いか(旅)、リフレッシュや娯楽が中⼼か(旅⾏)
うん、だいぶイメージに近づいてきた。 そう、“学び”や“⾮⽇常”の要素が強いもの。 物質的な移動よりも、精神の変化と結びつくもの。 それが、私にとっての「旅」だ。
そして、その「旅」を⼈⽣の軸として⽣きてきた⼈物がいる。 アドベンチャーフォトグラファーとして世界を⾒つめ続ける、福本玲央だ。
第⼀章 |リアルを⽣きるということ
「僕はリアルが⼀番⼤事だと思っている」。 福本玲央は、⾃らの⼈⽣の軸を“旅”に置いている。写真を⽣業にしながら、たとえ商業的な依頼であっても、必ず⾃分の中にテーマを置く。 ⾃分が向き合うことのすべてに、できる限り嘘を交えたくないという強い思いがある。 リアルさは、彼にとって⽣命線のようなものだ。
特にこのインターネット社会において、「リアル」を貫くのは容易ではない。 「夏までに痩せたい⼈、絶対⾒て!」「知らないと損するディズニー攻略法5選」。 特にディズニーに⾏く予定なんてないのに、強気なアテンションに惹かれて、気づけば集中⼒を削がれてしまう。
SNSの中だけの話ではない。 街中には、「どうにか私たちの商品を買ってください」とキャッチーな広告が溢れ、壁を埋め尽くしている。
ふと考える。私が⽣きていくのに本当に必要なものは、ふるさと納税以外にいくつあるのだろう。 悪意のある嘘ではないけれど、そこには“違和感”がある。そう、これは“純度”の問題だ。
その⾔葉は、⼝先ではなく⼼から出たものなのか。その⾏動は、⼼が⾜を動かした結果なのか。
福本の旅は、いつでも⼼に突き動かされている。 彼が10代のころから夢中になって旅を続けてきたあの感覚を今もずっと追いかけているということだ。 ⽬的地までの道程で⼿触りとして感じ る、⼼の表⾯のざらつき。 それをいかに⾃分のものにできるか――それが彼にとっての“旅”であり、⼈⽣そのものだ。
だからこそ福本はこう⾔い切る。 「隣⼈の部屋でさえ、好奇⼼に突き動かされる精神的な変化があれば、僕にとってはそれも旅の⽬的地になる」。 精神的な動きを旅と呼ぶのならば、⼈の話を聞いてそこに思いを馳せることも旅になる。 私はこのインタビューを通して、福本玲央という写真家の⼗五年、そしてこれからの⼆百年をのぞく旅をした。
第⼆章 | ベルーガを追う旅
福本は8⽉、北極圏のサマセット島へ⾶んだ。今回のテーマは「⽩イルカ」──ベルーガとの対峙だった。 1年の中でも限られた夏の時期、ベルーガは天敵であるシャチを避けて、出産と休息のために⼊江へと集まる。 その数、約2000頭。この地では毎年、その光景がひっそりと繰り返されている。
⽩い体に、微笑むような⼝元。
⽔族館で⾒るベルーガは、どこか⼈懐っこくてチャーミングな存在だ。 だが、福本が追い求めるベルーガは、単なる被写体ではない。 彼にとってベルーガとの邂逅は、⼈間と宇宙の神秘を結ぶ対話のようなものだった。 ベルーガをはじめとする鯨類は、⼈間と同じ哺乳類だが、その脳のサイズは⼈間よりもずっと⼤きい。 脳の⼤きさは、知性や記憶の深さに関わる。
⼀流の脳科学者は、 「⼤型の脳を持つ鯨類はどの⼈間よりも優れた知性を持っている」と説明した。⼈間以上に遠い視野で過去や未来を⾒つめて現状を考えることができるのだという。
計り知れないほどの優秀さを持つ彼らの脳には、祖先の経験や記憶が継承されているとされている。 つまり、ベルーガなどの鯨類はこの星の“記憶”を知っている。 地球の7割を覆う海のすべてを、彼らは感覚として把握しているのだ。 もしかしたらひとつなぎの秘宝の在処も、ワンピースの最終回の結末も。
そんなクリスタルスカルみたいな情報量を宿した彼らの頭の中がどうなっているのか、私たちの⼩さな脳みそでは想像することもできない。
ただ、全てを知る神秘の存在が、同じ世界に⽣きている事実。イルカやクジラと⼼が通じ合えば、世界は平和になる──
そんなロマンチックな⾔い伝えも残っている。だが、福本にとってそれは夢物語ではない。
「知りたい」「探りたい」「⾏ってみたい」。 その衝動こそが、彼にとっての旅の本質なのだ。
今回の旅の⽬的は、ベルーガの“声”を録⾳することだった。 “カナリアンドルフィン”と呼ばれるほど、彼らは⾔葉を持ち、歌うように会話をする。 その声を、記録として残す。それが福本の使命だった。 実際にベルーガと対峙し、声を録り、そこから何がわかるのか──答えがあるのかもわからない。 だが、好奇⼼がある限り、意味はすでに存在する。 もし2000頭のベルーガが集まった海で彼らの声を聴けたなら、⼈間の⼩さな脳は⼀体何を感じるのだろう。 その答えを求めて、福本は北極圏に⽴っていた。
第三章 | 無の極地で聴く⾳
結論から⾔うと──ベルーガの群れに出会うことは叶わなかった。
バギーに乗って8時間も探索をしてみたり、ドローンを⾶ばして上空から海を覗いたり。そんな9⽇間だった。
けれど、条件が合わなかった今回の旅の中では、彼らの姿を⾒ることはできなかった。 ただ、それでもこの旅には意味があった。
むしろ出会えなかったことで、福本は「地球を聴く」というもうひとつの旅をしていたのだと思う。
- ベルーガを見つけることはできたが、群れには出会えなかった。 -
ドローンから⾒たサマセット島の景⾊は、あまりにも広く、距離の感覚がつかめなくなるほどだった。
緑がほとんどない場所では、「無の極地」という⾔葉がぴったりくる。 太陽が沈まないこの地では、昼がずっと続く。
つなぎめのない時間が、ゆっくりと流れていく。 「四季があるとまでは⾔いすぎですけど、それに近いくらいの変化を感じました」福本はそう語る。 ⽇差しが差すとポカポカと暖かく、⾵が吹けばマイナス5度の世界に⼀瞬で引き戻される。 ほんの数⽇前までは氷に覆われた惑星ホス。
地表があらわになり、今はまるでナメック星のようだ。 歩きながら、そこらじゅうに散らばる化⽯を⾒つけては、「これが地球か」と⾔いたくなる。 宇宙から眺めなくても、この場所に⽴っているだけで“惑星”の存在を実感できる。 地球丸ごとここにある──そんな感覚だ。
やがて福本は、静寂に気づく。⾵の⾳も、⼈の声も、なにもない。 まるで⼈⼯的な無⾳空間に閉じ込められたような錯覚。 ここに⾝を置くことは体にとっていいことなんだと、なぜだか確信できた。 マイクを通すと、⼩川のせせらぎ、⾵の通る⾳が微かに聴こえる。 ⽿では拾えない⾳たちが、世界の隅々に漂っている。 寝転がって空を⾒上げると、視界いっぱいに⻘が広がる。 空と⼤地が合わせ鏡のように響き合って、⾃分がどちらにいるのかわからなくなる。 無⾳空間の中で溶け出して、この地と福本は⼀体になる。 その後に残るのはきっと、愛とか、そういう重さのあるものだけだった。
静寂の中で、福本は1時間ほど、ただそこにいた。 待っていたわけじゃない。でも、“ここにいるべきだ”という感覚があった。 そのとき、川を渡る麝⾹⽜(ジャコウウシ)の姿が⽬に⼊った。 思わずシャッターを切る。
以前、先住⺠の神話を追う旅の中で聞いた話がある。
「麝⾹⽜が神聖な川を横切るとき、幸運なことが起こる」──と。今、⽬の前にその光景が現れた。
この「幸運」というのは、この旅の中でベルーガに出会えるとか、宝くじが当たるとか、そういう話じゃない。
このあと⾷べるごはんがやけに美味しく感じたり、家族の「おかえり」がいつもよりあたたかく響いたり。
そういう、受け取る側の感性があって初めて完成する、そういう種類の幸運のことなんじゃないだろうか。
第四章 | ⼈類から環境を守るという責任
⼩学⽣の頃、「環境を守ろう」というテーマでポスターを描かされたことがある。 その時から、どこか違和感があった。 ⼦どもながらにみんな「ポイ捨てをしない」とか「ゴミを分別しよう」とか書く。 でもそれって、どちらかというと倫理の話じゃないか。 ⽣きていく上でのマナー的なことを掲げて、それを「環境を守る」と呼ぶのは、どうも腑に落ちなかった。 「環境を」という上の句には、「守る」という動詞がついてくるように刷り込まれてきた。 でも、そもそも環境って、私たちに“守られる側”なのだろうか。 破壊を続けるのは⼈間でその⼈間が「守るぞ」と声⾼に⾔う姿は、引きで⾒たら滑稽とさえ思える。 ⼤きな悪の中の、表⾯だけの正義。偽善という⾔葉が似合う光景。
──サマセット島のロッジは、こんな⽭盾に対してのひとつの答えのように存在している。
サマセット島のカニンガム⼊江には、かつて政府の研究者たちがベルーガの調査拠点として使⽤していた⼩さな施設があった。しかし研究予算の削減によって常設活動が続けられなくなり、現地から撤退した。 その後、カナダ⼈探検家夫妻がこの地の使⽤権と旧施設を引き継ぎ、再建と拡張を経て現在のロッジの形を作り 上げた。 訪問者数は環境負荷を抑えるために年間で⼈数が限定されており、そこで得られる収益は再びこの場所の保全と 維持に使われている。
まるで呼吸のような循環だ。 「環境を守る」という⾔葉を、初めて実感として理解した気がした。 この星を「惑星だ」と感じる瞬間、福本はひとりの“地球の記録者”としてそこにいたのだと思う。 無の極地に吹く⾵や、凍てつく空気の質感を、そのまま持ち帰るために。
そして、もうひとつ。このロッジには副次的な仕組みがあった。 滞在費は決して安くない。必然的に訪れるのは、発信⼒を持った富裕層や、社会を動かす⽴場の⼈々だ。 彼らがこの地に⾝を置き、“地球という存在”に触れる。 その感覚を街に持ち帰った時、何かが変わるかもしれない。強制ではなく、⾃然な形で──。
あるものをあるままの姿で循環させる。
その思想は、BRINGの理念に重なる。「地球を、着まわせ。」 BRINGが、繊維から⽣まれた再⽣ポリエステルを使い、回収・再⽣・再構築というサイクルを回すように、 このロッジもまた、⾃然と⼈のあいだにある循環の装置なのだ。 福本がこの地に魅せられた理由。そしてBRINGの服に惹かれる理由。 根の部分はきっと、遠いものではないはずだ。
第五章 | すべては繋がっている
私たちの存在が、地球にとってどういうものなのか。 考えるたびに、少し居⼼地が悪くなるような感覚がある。 ⼈類が“快適さ”を追い求めれば追い求めるほど、私たちの家──地球が持つ再⽣機能は衰えていく。 きっと根本的な部分からもう⼀度考え直さなければならない。鯨類は、この星の7割を占める海の多くを知っている。 彼らの脳は、ヒトよりも⼤きい。祖先の記憶や、海の出来事がすべてその中に刻まれる。
彼らは⼈類とこの星の⾏⽅を、どう⾒ているだろうか── そもそも地球を破壊している、という考えそのものが烏滸がましいのかもしれない。 ⼈間は征服者ではなく、この惑星の中の⼀時的な通過者にすぎない。 数の⼒に頼りすぎて、⾃分たちの作ったルールの中で“えらくなった気”に なっているだけだ。 「⼈間は、⾁体としてそんなに進化しないのかなと思う」福本はそう⾔っ た。 だからこそ、私たちはクラフトしてきた。服をつくり、家をつくり、道具をつくり、知恵を重ねてここまで来た。 でも、それも地球の歴史の中ではほんの⼀瞬の個性にすぎない。 ベルーガは、服を着ていない。パソコンをいじってもいない。 ただ、優雅に、穏やかに、⼝元に⼩さな笑みを浮かべて海を回遊している。 その姿こそが、私たちが向かうべき“答え”なのかもしれない。
「ひとつだけ明確に⾔えることがあるとするならば、全部繋がっていると思うんですよ」 福本はそう⾔った。 サマセット島の⼊江に流れ込む氷の温度は、知床の流氷と繋がっている。この空の果ては、私たちの住む空とも地続きだ。 それは物質的なことだけではない。 初めて出会った⼈の中に、なぜか⺟のぬくもりのような懐かしさを感じたり。 前の旅で探していた答えが、地球の裏側でふいに⾒つかったり。 世界はいつも、そうやって繋がっている。 私たちの“記憶”という装置が、その⽷をたぐり寄せているのだ。 あっているか間違っているかわからないレベルの、⾃分⾃⾝の“解釈”を信じること。 その不確かさの中で⾒えないものを信じて⽣きていける、ヒトという種族。 そう考えると、ベルーガよりも脳の⼩さな⼈間の鈍感さが、愛おしく思えてくる。
旅をして、滞在する⼟地を変えたときの本質的な変化は“場所”ではなく“感じ⽅”だ。 物質的な移動よりも、⼼の輪郭が揺らぐことの⽅が、ずっと⼤きい。 数えきれないほどの旅を重ねてきた福本が「すべては繋がっている」と⾔い切る。 それは、私にとってものすごく⼤きな希望だった。会社に⾏くのが少し憂鬱な朝も、⼭を静かに歩く週末も、すべては⾃分という輪郭を軸につながっている。 私がいま北極圏の話を聞いているこの瞬間も、この記事を読んでいるあなたの呼吸も、全て北極圏に繋がって、 あの海に放り出される。 それは、⼈が⼈であるがゆえの、ベルーガからしたら⼩さな悩みの、ひとつのアンサーなのかもしれない。
第六章 | 純度の⾼い⼈間として⽣きる
福本玲央という⼈を⼀⾔で表すなら、「純度の⾼い⼈間」だと思う。嘘がつけないのだ。
商業的な依頼であっても、⾃分の中のテーマを⾒いだせないまま進めることができない。
「できるだけ嘘はつかずに」彼はそう⾔う。 だからこそ、彼の作品や⾔葉には意味がある。
思考の純度が⾼く、フィルターを通さずに届いてくる。その曇りのなさが、⾒る⼈の⼼をまっすぐに射抜く。
彼の⽬指しているのは、⽣きている間の評価ではない。 それよりもずっと先、200年後の未来だ。
「⾃分の作った写真集を、200年後に残したい。そのとき“200年前はこんな⼈がいて、こんなに綺麗だったんだ”と思ってもらえたら、そう思ってもらえなくても、“⼤切なことを次の世代へ繋ぐ記録”として残ったら嬉 しい。」
200年後、福本⾃⾝はもういない。そして福本が⽣きた時代を知る⼈も、誰もいない。
それでも作品が“地球の記録”として残るなら、それはきっと、彼の存在そのものになる。
「物質を⽣み出すことは、究極的にはゴミを増やす⾏為かもしれません。でも、意味を持たせることができたらと思うんです」
ほとんどの⼈は、⽣きているうちに褒められたい。数字や肩書きで評価されたい。
でも福本は、そこから欲を切り離す。
だからこそ、彼の作るものには不純物がない。
「なんでそんなに真っ直ぐでいられるんですか?」と尋ねたとき、福本は少し考えてから答えた。
「選択しているんです。⽣まれつき何かに突出しているわけじゃなくて、バランス感覚の問題だと思っています」 ここで定義した「純度」の低い考えが浮かぶこともある。 でもそのたびに、⾃分の中で柔らかく“選び直す”のだという。 ⽣まれたときからまっすぐ、顔に“⾃分が正しい”と書いてある⼈もいる。 でも、福本からは尖った印象をまったく受けない。
どこまでも穏やかで、丁寧な⼈だった。
彼にとって、写真も服も旅も、すべては⼿段だ。 「どこかに属する」のではなく、⾃分の好奇⼼に正直であり続けるための道具。 相⼿がきちんと⽿を傾けてくれる場であればスーツを選ぶし、汚いTシャツの⽅が届くなら迷わず汚れたTシャツを着る。すべては、好奇⼼に駆られた福本の、表現のための選択にすぎない。 好奇⼼に導かれるまま、これまで点として存在してきた旅が、 いま福本の中で⼀本の線に繋がっていく。 全てが彼の探究したい神秘に向かって、収束していくのだ。
福本が表現の⼿段として「写真」を選んでいることも、彼の性質と深く結びついている。 写真とは、⽬の前の景⾊をそのまま写す⾏為。
その正確さは、まるで“歪みの少ない鏡”だ。
昔読んだ⼩説『⾈を編む』にあった⼀節を思い出す。 「たくさんの⾔葉を、可能な限り正確に集めることは、歪みの少ない鏡を⼿に⼊れることだ。歪みが少なければ 少ないほど、そこに⼼を写して相⼿に差し出したとき、気持ちや考えが深くはっきりと伝わる。」 写真もそれと同じだと思う。歪みのない鏡として、福本は世界をまっすぐに写す。 「相⼿に委ねている部分もあるので、ちょっとずるいですけどね」と、福本は笑った。 でも、その“ずるさ”の奥には、感性とプライドがある。 余⽩を残して、⾒る⼈に解釈を委ねる。その潔さこそが、彼の誠実さだ。
最後に、彼はひとつの話をしてくれた。
サマセット島からの帰路、イエローナイフの町から⼩型機で⼀時間ほど離れた湖に、友⼈と滞在した。 湖畔に寝そべって夜空を⾒上げていたとき、友⼈は僕にこう話した。 「レオがやっていることや、感じていることは、とても稀有なことだよ。だから伝えないといけない。」
⾃分の考えていることなど理解されるはずがない。そう思い込んでいた福本は、“伝える”という⾏為そのものか ら⽬をそらしてきた。その⾔葉が胸に深く突き刺さりながらも、やはり伝えることは難しい。
反芻する友⼈の⾔葉が頭の中を巡る中、視界では夜空に薄い⻩緑の光を捉えていた。 その光は波を打つように⼤きく、濃くなり、やがて視界を埋め尽くした。 空いっぱいに広がる光のカーテ ン。「オーロラが⽌まらない」としか⾔いようのない光景だった。 ⼤きな⽯がごろつく湖畔で⼤の字になり、⽌まらないオーロラを浴び続けながら、 友⼈は⼩さく笑って⾔った。
「レオ、これは. さすがに伝えられないね。」 どんな語彙も、どんな写真も、今⽬の前に広がるこの光には到底届かない。 そこに⾝を置いた者だけが触れられる、特別な瞬間。 ⽌まらないオーロラを眺めながら、友⼈はもう⼀度つぶやいた。 「でも、レオ。ちゃんと伝えないとね。」
⾃分の⽬だって、今⽬の前の全てを拾えているわけではない。 ただその場に“いる”ことだけが、全てで。 その時間は、彼にとってボーナスのような時間だったのだろう。 正直に⽣きてきた⼈間だけが受け取れる、⾛⾺灯を彩る⼀ページ。
「伝えたい」「伝えなきゃ」福本はインタビューの中で何度もそう⾔った。 その思いを受け取った以上、私はそれを“⽂章”にしなければならないと思った。 純度の⾼い⾔葉を、できる限りそのままの温度で伝えたい。 写真が、⽂章が、その作品の中に込められるものは限られている。 でも嘘がなければ、純度が⾼ければ、伝わるものは必ずある。
なぜ残したいと思うのか、なぜ伝えたいと思うのか。その問いに、明確な答えはない。 けれど、その“わからなさ”にこそ、⼈が⽣きる意味が宿るのだと思う。 この海と同じように、私たちの思考もまた、深くて、神秘的で、⾔葉にしきれないほど美しい。 200年後、誰かがこの福本の記録を⼿に取り、その世界に触れたとき、 彼はきっと、笑っているだろう。
[WUNDERWEARとともに歩いた旅]
福本がこの北極圏の旅でまとっていたのは、BRINGのベースレイヤー。 氷点下と⽇差しが同居するサマセット島では、「寒さ」と「汗」は交互にやってくる。 体温を守りながら、動いたあとの汗冷えをいかに防ぐか。ここで活躍したのが、WUNDERWEARシリーズだ。
BRINGが福本玲央を応援する理由 彼の旅を⽀えてきた“純度”と“循環”の感覚は、BRINGが⼤切にしている思想と同じ温度を持っている。 今ある地球の姿を、できるだけそのままの形で未来に
⼿渡したい。 服作りに乗せたメッセージで「地球を、着まわせ。」と提案するBRINGと、 写真で地球の記録を残そうとする福本の旅は、⼿段は違えど同じ⽅向を向いている。 福本玲央という存在は、仲間としてBRINGは応援したいと願うのだ。
今回の旅をともにしたレイヤリングは、以下である。
-
WUNDERWEAR シームレス クルーネック
肌に直接触れる⼀枚。⻑時間の移動や撮影でもごわつかず、汗をかいてもベタつきにくい。 「とりあえずこれを着ていけば⼤丈夫」と思える安⼼感のあるベース。
-
WUNDERWEAR シームレス フーディー
体温調節⽤の⼀枚として。フードを被るだけで⾸まわりの冷えをふっと和らげてくれる。 バギーの移動中や⾵の抜ける稜線で、さりげなく⼼強い存在。
-
WUNDERWEAR レギンス
⾜元が冷えると、旅の気⼒まで持っていかれる、、、 そんな状況でも、動きやすさと暖かさのバランスを保ってくれたレイヤー。 ⻑い北極圏の⼀⽇を⽀える、影の⽴役者。
あわせて読みたい
いま話題の記事