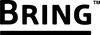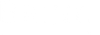BRINGは、高尾山にある直営店「BRING CIRCULAR TAKAO」の回収ボックスや、オンラインストアの商品購入者様にお送りしている回収封筒、さらには回収パートナーの店頭などで、どなたでもご参加いただける衣類回収を行っています。
使用済みウールをリサイクルし、高品質な再生ウールを作り出す。毛織物の産地、尾州地域で反毛工場を取材しました!
2025.8.8
回収された衣類は、自社工場の北九州響灘工場をはじめとする分別拠点へ集められ、市場の需要に合わせて、リユース・リサイクルへ分別されます。リサイクルされる衣類へと分別されたものは、各リサイクルパートナーの工場へと送られます。
今回はそれらの工場のうち、ウール製品を反毛し、再生ウール糸へとリサイクルする、愛知県一宮市の株式会社サンリードと大和紡績株式会社を取材しました。
貴重な反毛機やミュール紡績機を使用した、再生ウール製造を解説!
リサイクル工程①:選別、不用物の除去(サンリード)
サンリードには、廃棄された古着、衣類の製造段階での残布、裁断くずなどが原料として納入されます。古着は編み方に関わらず、ウール80%以上のものが選別されています。ほとんどが廃品回収や不用品回収のエコボックスに捨てられたもので、回収量は月によって増減しますが、冬物を衣替えで整理する5月が一番多いそうです。サンリードでは、月に12、3トンの原料が処理されています。
入ってきた古着等は色分けを行い、リサイクルできない不要なものを除去します。チャックやボタン、タグ、ポリエステルの紐なども、ハサミを使って手作業で取ります。取り除かれたもののうち、ボタンは再利用され、布類は自動車内装材にリサイクルされるため、捨てるものはほとんどないそうです。
色分けは50色くらいに行います。例えばピンクでも、薄ピンク、中ピンク、濃ピンク、ローズピンクなどに分けられます。分類された衣類、残布、裁断くずなどは色ごとにまとめられ、次の反毛の工程へと進みます。
株式会社サンリード 取締役社長 南 正明さんにお話を伺いました。
リサイクル工程②:粉砕、反毛の製造(反毛工場)
仕分けられたウールに、まず「油打ち」という生地にオイルを染み込ませる作業を行います。裁断前にオイルと水につけて生地を柔らかくすることで、機械に通す際に静電気が起きたり、毛が切れてしまったりすることを防ぎます。梅雨の湿気が多い時期は水分を減らすなど、オイルと水の量は職人さんの長年の経験により調整されているそうです。
油打ちされた生地は破砕機による裁断後、ラックマシーンより粉砕されます。さらに、ガーネット機(反毛機)で、前に回転するローラーと後ろに回転するローラーの間を通るうちに、少しずつほぐれていって、最終的には羊毛とあまり変わらないほど、ふわふわの状態になります。出来上がったものを素手で触って確認し、状態が良くなければ、もう一度この工程を繰り返します。
機械のスピードは、早くするときは繊維が太いもの、遅くするときは繊維が細いものというように、原料の性質により変えています。1日に200kgくらい、綿状の反毛が出来上がるそうです。
リサイクル工程③:紡績(大和紡績)
最後は、反毛綿から糸を紡ぐ作業です。
まずはクライアントの注文に合わせて、いくつかの反毛綿を混ぜ合わせる「調合」を行います。油通しをしながら、ゆっくりと何回も混ぜ合わせます。
例えば紺色を作るにも、黒っぽい紺や青っぽい紺、黒など様々な色の反毛綿を混ぜ合わせ、立体感のある色に仕上げています。その時々の古着や裁断くずの色によって、出来上がる反毛綿の色もわずかに変わってくるため、同じ反毛綿が無くなった場合は、他のいくつかの反毛綿を混ぜて、その色に似た色を作り出します。調合の資料は、15年分くらいは残しておき、次に同じ色の糸のオーダーが入った際の参考にします。熟練の職人さんが調合することで、異なる原料を使ったとしても、クライアントの満足する色を作り上げることができるそうです。また、この調合の正確さは、古着や裁断くずの色分けをする際、細かく色を分けているからこそできることだといいます。
調合された反毛綿は一枚の大きなシート状になり、それをゴムとゴムの間を通すことで、「絲(しの)」と呼ばれる、細い糸状のものができます。この段階ではまだ糸に撚り(より)がかかっておらず、引っ張るとブツブツと切れてしまいます。
そこで最後に、「ミュール」という機械で糸を引っ張り、伸ばしながら撚りをかけることで、糸を仕上げていきます。内側から外側に撚りをかけることで、引っ張っても切れない強い糸になっていくそうです。一定の撚り合わせが完了すると、機械が自動的に止まり、巻き取りが始まります。約2時間の運転で、60kgほどの糸が出来るそうです。
反毛綿から作られた糸は「紡毛糸(ぼうもうし)」と呼ばれ、空気を含んだようなボコボコとした糸になります。紡毛糸は柔軟で温かいのが特徴で、セーターやコートを作る際に適しています。バージン・ウール※1でも、羊のどの部分の毛をカットするかにより、「紡毛糸」と「梳毛糸(そもうし)」(繊維が長く整っており、ツルツルとした肌触りの糸)に作り分けられ、それぞれ適した製品へと使われているそうです。
出来上がった糸は、太い糸、細い糸がないか確認し、太さが整えられた後、束にまとめて出荷されます。そして織物工場に送られ、再生ウールの生地へと加工されていきます。
※1 バージン・ウール:再生ウール等を使ってない、新しい羊毛で作られたウール。
大和紡績株式会社 代表取締役社長 保浦 祥克さんにお話を伺いました。
尾州地域で半世紀以上続く、再生ウールを使ったものづくり。
愛知県一宮市を含む尾州(びしゅう)地域は、「木曽三川」と呼ばれる木曽川、長良川、揖斐川の3つの大きな川の水源に恵まれ、ウールの糸に適した約60%の湿度を保つことができる気候だったことから、国内最大の毛織物産地として発展してきました。
のこぎりの歯の形に似た三角屋根の建物は、紡績・織物・染色関係の産地に多く見られます。
再生ウールの製造は、70年ほど前から続いています。最初はバージン・ウールの価格が高いため、リサイクルのものを混ぜてコストダウンすることから始まりました。繊維には必ずくずが出るため、回収して、それを混ぜてウール糸を作っていたそうです。再生ウールを70%、強度を高めるための化学繊維(ナイロンなど)を30%使い、糸を作っていたことから「毛七(けしち)」という名称で呼ばれ、流通していましたが、それが近年サステナブルな取り組みとして、注目され始めたということです。今回取材した大和紡績では、ウールにブレンドするナイロンもリサイクルされたものを使っています。
再生ウールは元々色のついた原料から作られるため、染色工程が必要ないことも製造工賃を下げ、再生ウールが重宝されてきた理由の一つです。バージン・ウールを染めるために必要な水を節約し、CO2の排出を削減することで、地球環境にも優しい製造方法となっています。
一方、再生ウールには、原料の色によって、作り出される糸の色に偏りが出るという難点もあります。カラフルな色の原料は数が限られ、多いのは紺、黒、グレー、茶色といったベーシックな色のものです。柄が入ったセーターなどは、一本ずつ糸をほどくことができないため、一度黒く染めてから反毛しています。おのずとベーシックな色の糸を作ることが多くなりますが、そこにピンクや青といった色ものを少し混ぜることで、特徴的な色の糸を作り出すこともできるそうです。これは、バージン・ウールには出せない色合いとして、再生ウールの大きな魅力となっています。
再生ウールは、製造ロットにより僅かな色の違いが出ることが、製品化におけるハードルになっていました。けれども近年は、それが再生ウールの”味”として製品に活用されることも増えているそうです。今回の取材を通じ、リサイクルされたものならではの品質や特徴を理解して、それを活かした製品づくりをすることが大切なのだと学びました。
また、尾州地域では古くから続く繊維工場がなくなっていき、跡を継ぐ人材も減ってきていることから、伝統的な技術の存続が難しくなってきています。使用している機械が壊れた際は、修理に出すところもないので、職人さん自らの手で直しているそうです。こういった状況は、日本各地の伝統産業で起きていることだと思います。日本の産業を知り、できる限り日本で作られた製品を使っていくことが、伝統産業を守る一つの手段になるのではと感じました。
「旧・尾西繊維協会ビル」を活用した「Re-TAiL」。尾州の布地が集まるマーケットや、衣類のオーダーメイド店などが入っている。
株式会社サンリード
大和紡績株式会社
愛知県一宮市浅井町尾関字同者168番地
BRINGの衣類回収について
取材・執筆:熊沢紗世
あわせて読みたい
いま話題の記事